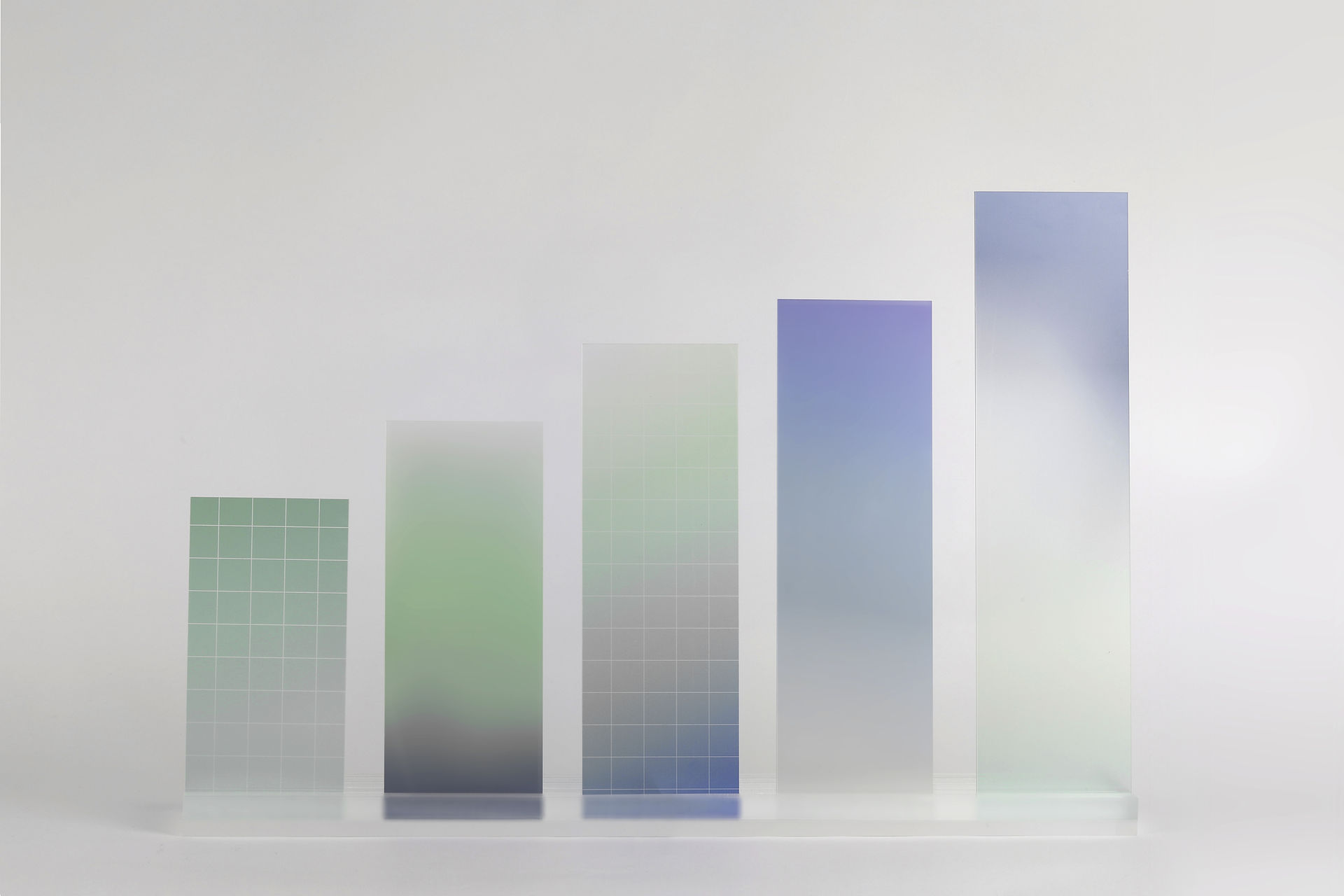

キュビスム芸術史
2019年2月
単著
第32回「和辻哲郎文化賞」受賞
名古屋大学出版会の紹介文
「絵画、彫刻、文学、建築などの作品においても、理論や批評の言説においても、多面的かつ国際的な拡がりをもつキュビスム。「幾何学」的表現の誕生・深化から、二度の世界大戦を経て、歴史的評価の確立へと至る曲折に満ちた展開を、美術と〈現実〉との関係を軸に描ききる。」
古宗教遺産テクスト学の創成
2022年3月
分担執筆(木俣元一・近本謙介編)
出版社の紹介文
「「祈り」という人類の普遍的・根源的営みのなかで構築された宗教は、それを信仰し担う人々により、多種多様な形をもって大切に守られ、伝えられてきた。また、一方で、人間と宇宙の根源的な在り方を規定する拠り所であるが故に、世界認識における解釈の対立を生じさせ、時には宗教間の軋轢や破壊を呼び起こすきっかけともなった。
「宗教遺産テクスト学」とは、人類によるあらゆる宗教所産を、多様な「記号」によって織りなされた「テクスト」とみなすことで、その構造と機能を統合的に解明し、人類知として再定義することを目的とし、「コト」と「モノ」を一体化する新たな学術領域である。
宗教遺産を人類的な営みとして横断的かつ俯瞰的に捉え、ひと・モノ・知の往来により生成・伝播・交流・集積を繰り返すその動態を、精緻なアーカイヴ化により知のプラットフォームを構築することで、多様性と多声性のなかに位置づける。
文理を超えた三篇七章、四十の論考により示される、人類の過去・現在・未来をつなぐ新視点。」


Paysage(s) de l’étrange II
Arts et recherche sur les traces des patrimoines de guerre dans le monde
2023年6月
分担執筆(Aurélie MICHEL・Susanne MÜLLER編)
内容
Quel patrimoine reste-t-il après les guerres ?
C’est notamment par le biais de l’art que les différents textes rassemblés ici abordent les conflits historiques depuis 150 ans et leurs traces laissées dans le présent. Les différentes formes de création, sont en effet à même de s’emparer de la mémoire des récits parfois lacunaires, pour en révéler les manques et en proposer une lecture inédite.
Les contributions interdisciplinaires de cet ouvrage prennent appui sur une matière immédiate : le paysage. Pourquoi ? Parce que ce dernier porte les stigmates des conflits, mais tend aussi à effacer progressivement ces empreintes. En constante mutation, le paysage reflète, à chaque moment donné, l’histoire qu’il a traversée. La notion d’étrange est envisagée comme ce qui fait rupture avec l’environnement connu, le bouleverse, l’inquiète et le transgresse.
Suite à une guerre, une annexion, occupation ou autre forme de confrontation violente le paysage garde des traces étrangement inquiétantes, qui font irruption dans un contexte paraissant familier, mais qui devient tout à coup différent, lointain. Les textes réunis ici font apparaître cette dimension particulière, provoquant une sorte de tiraillement ou de va-et-vient entre ce qui fait sens, logique et s’en échappe dans un même mouvement.









